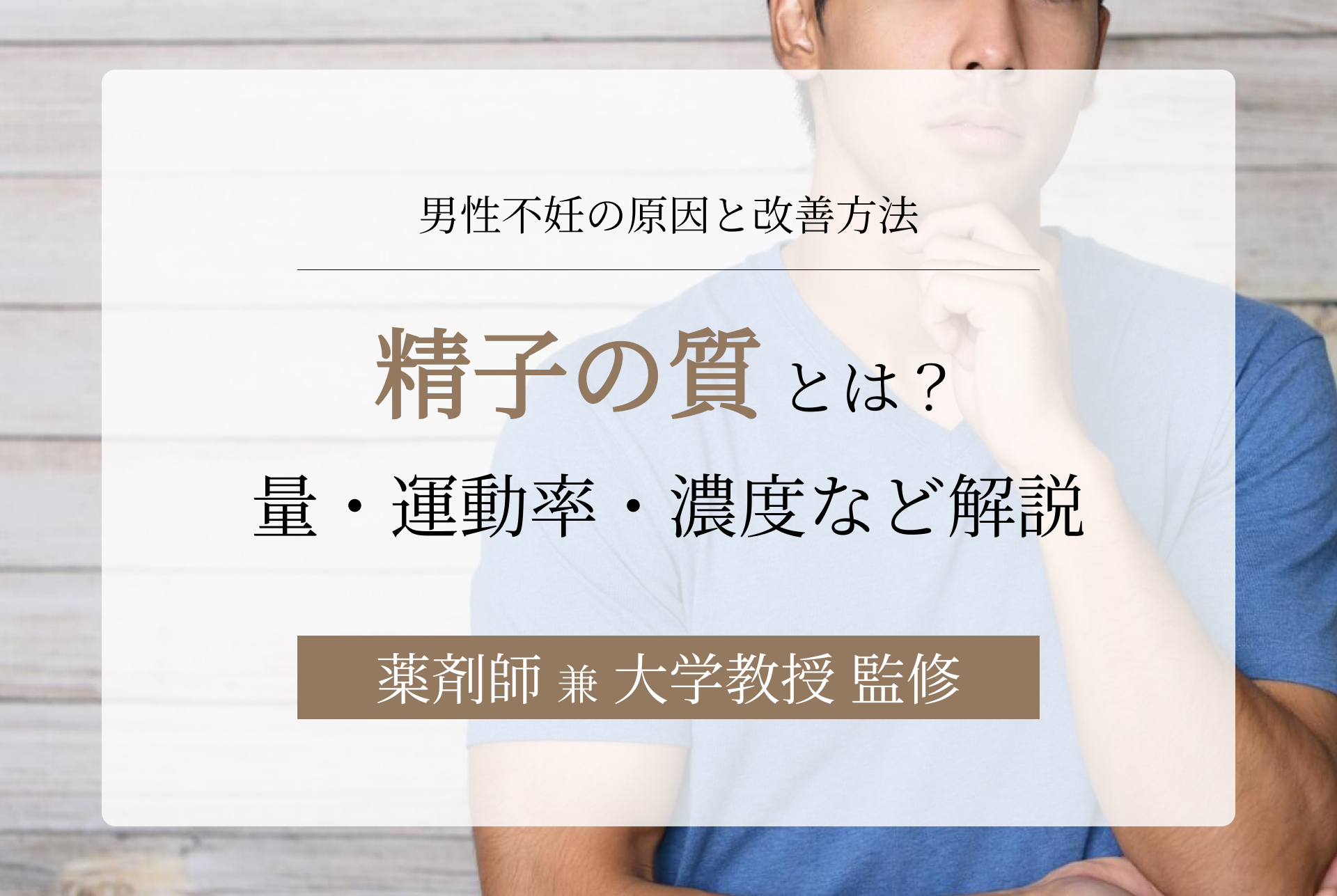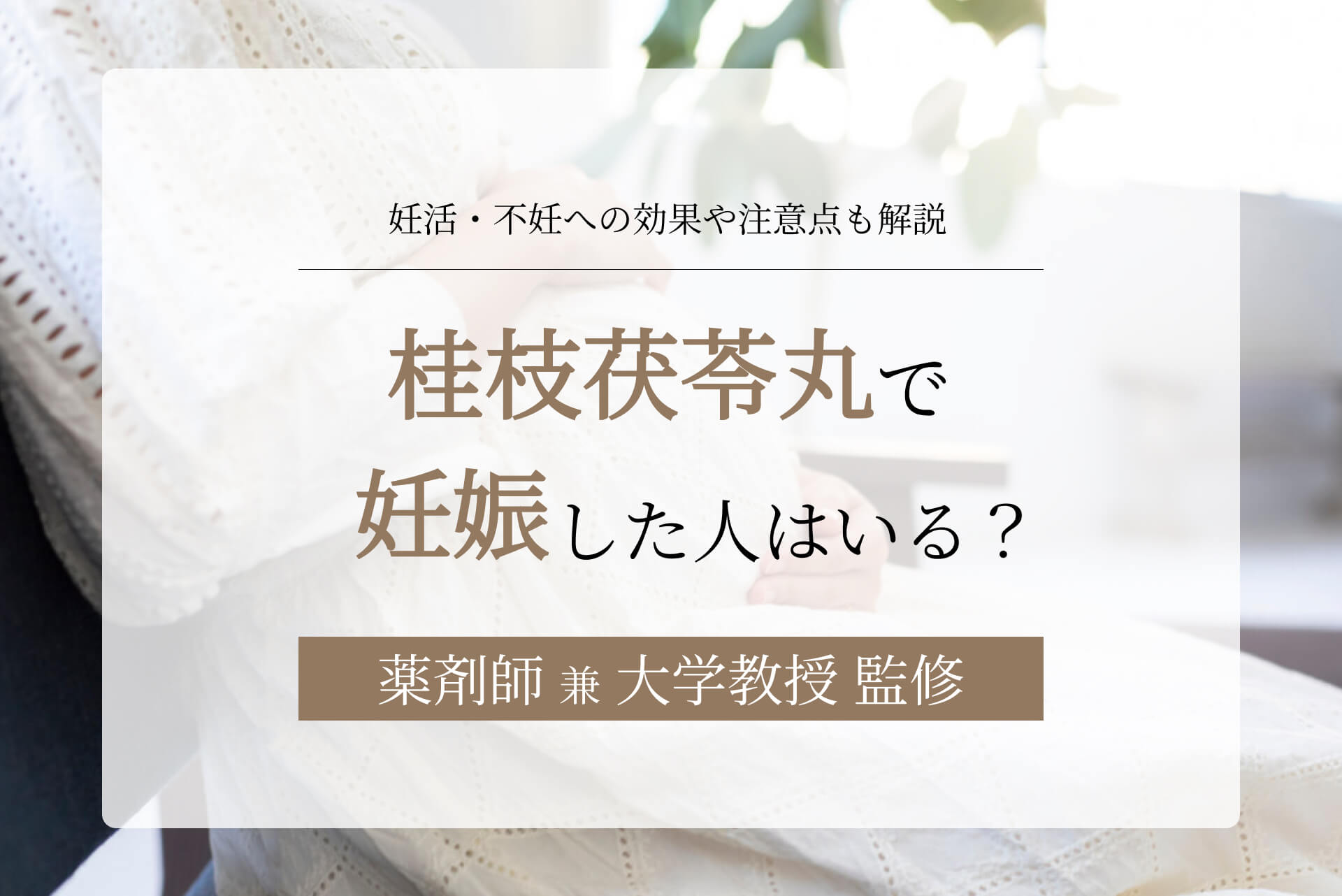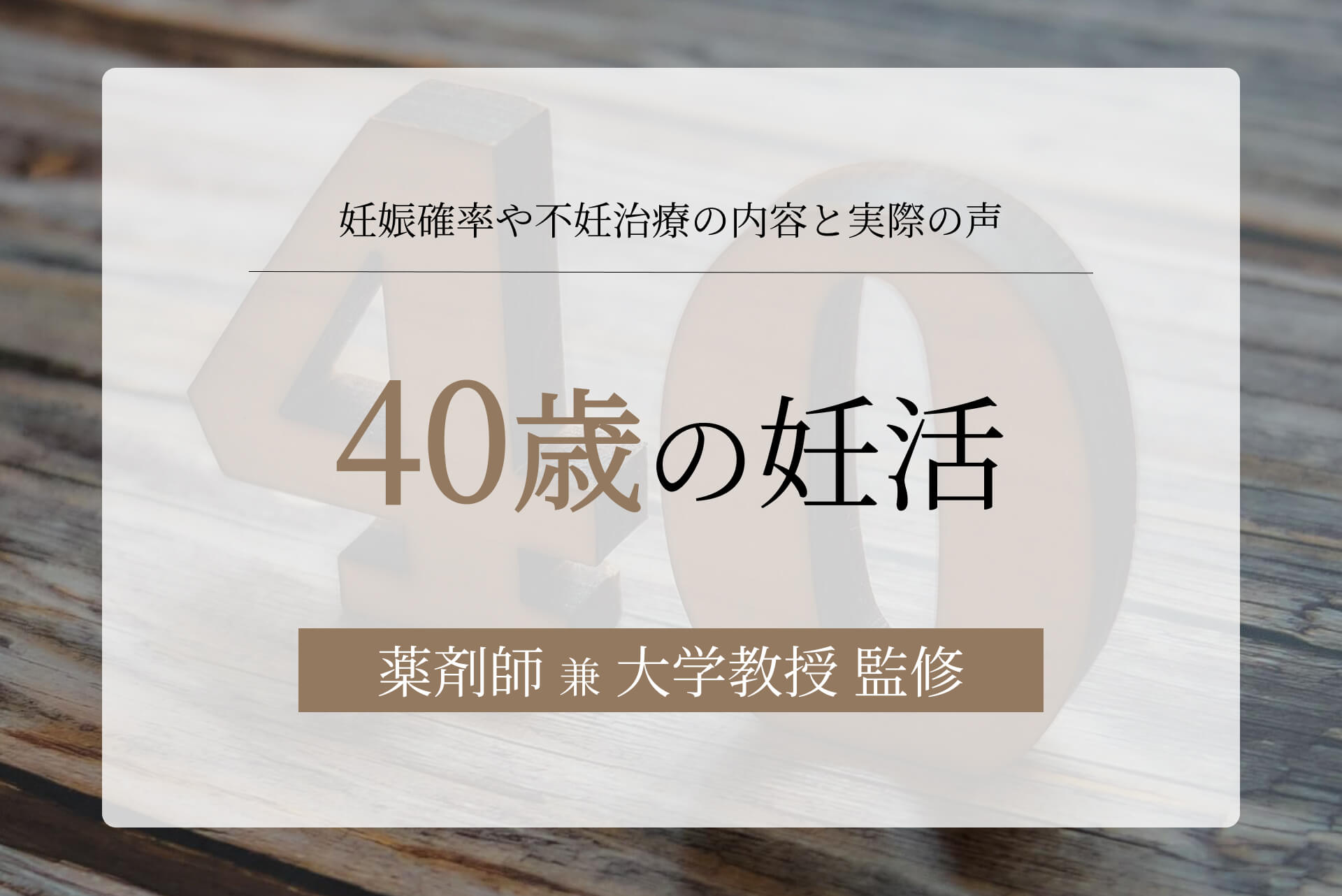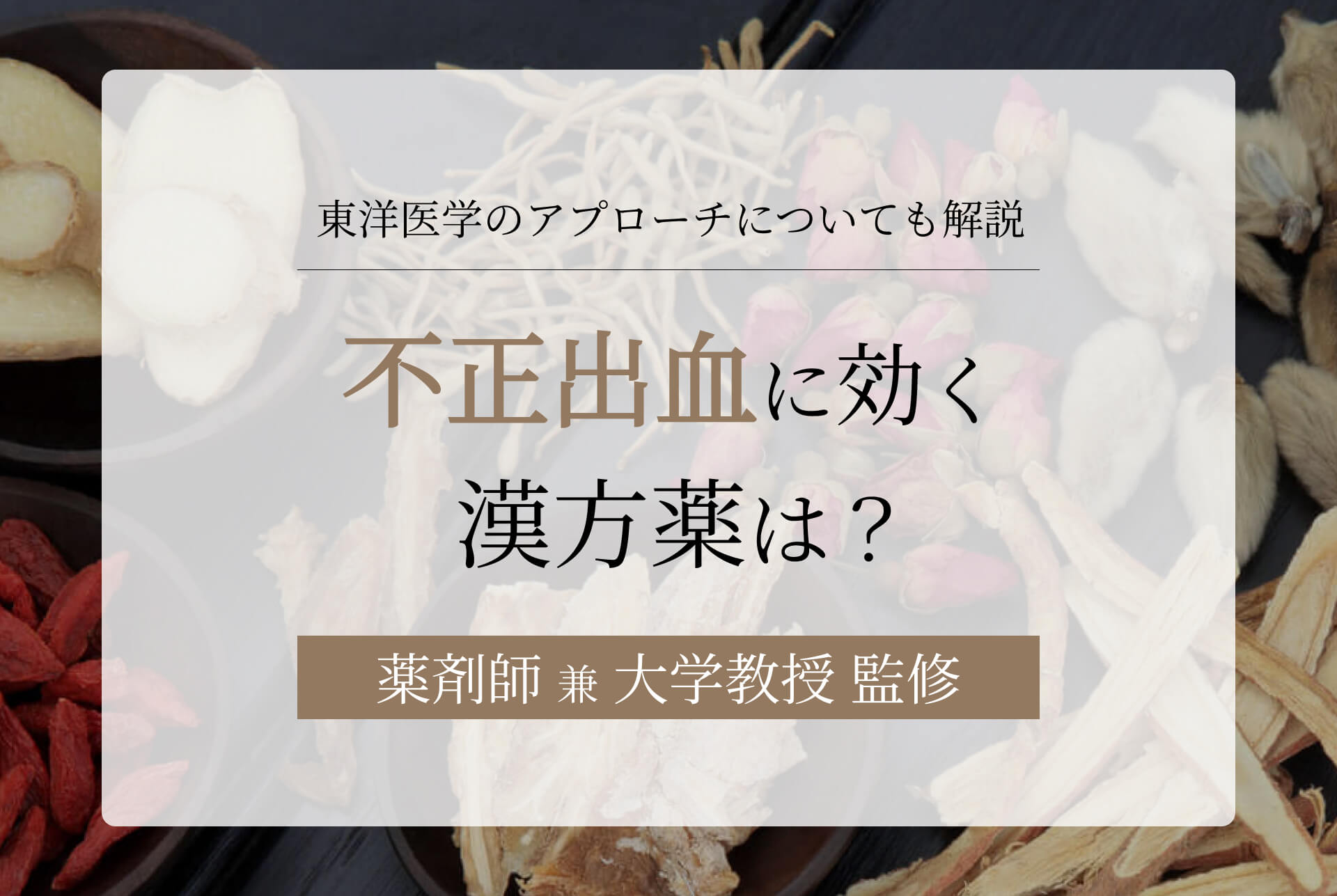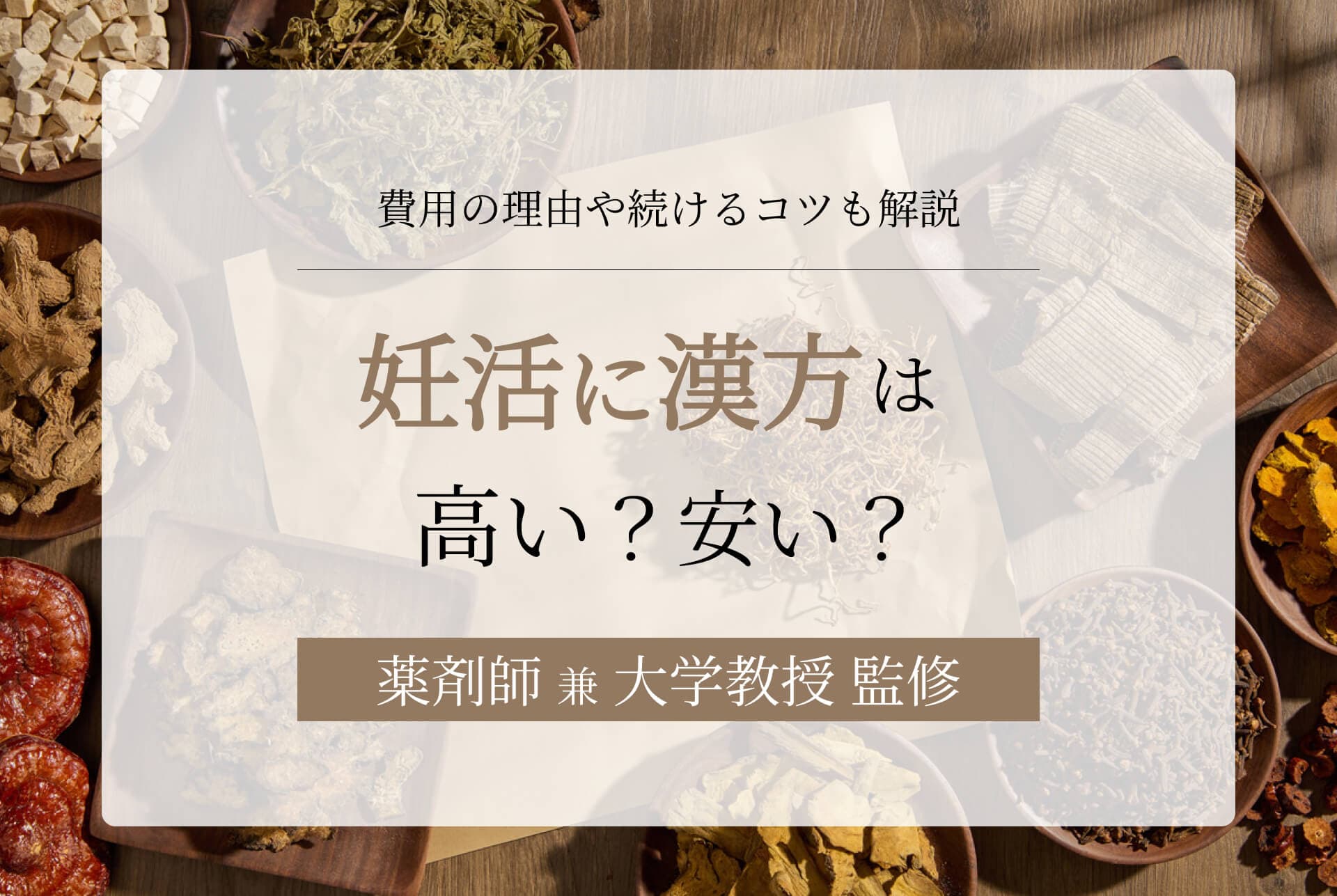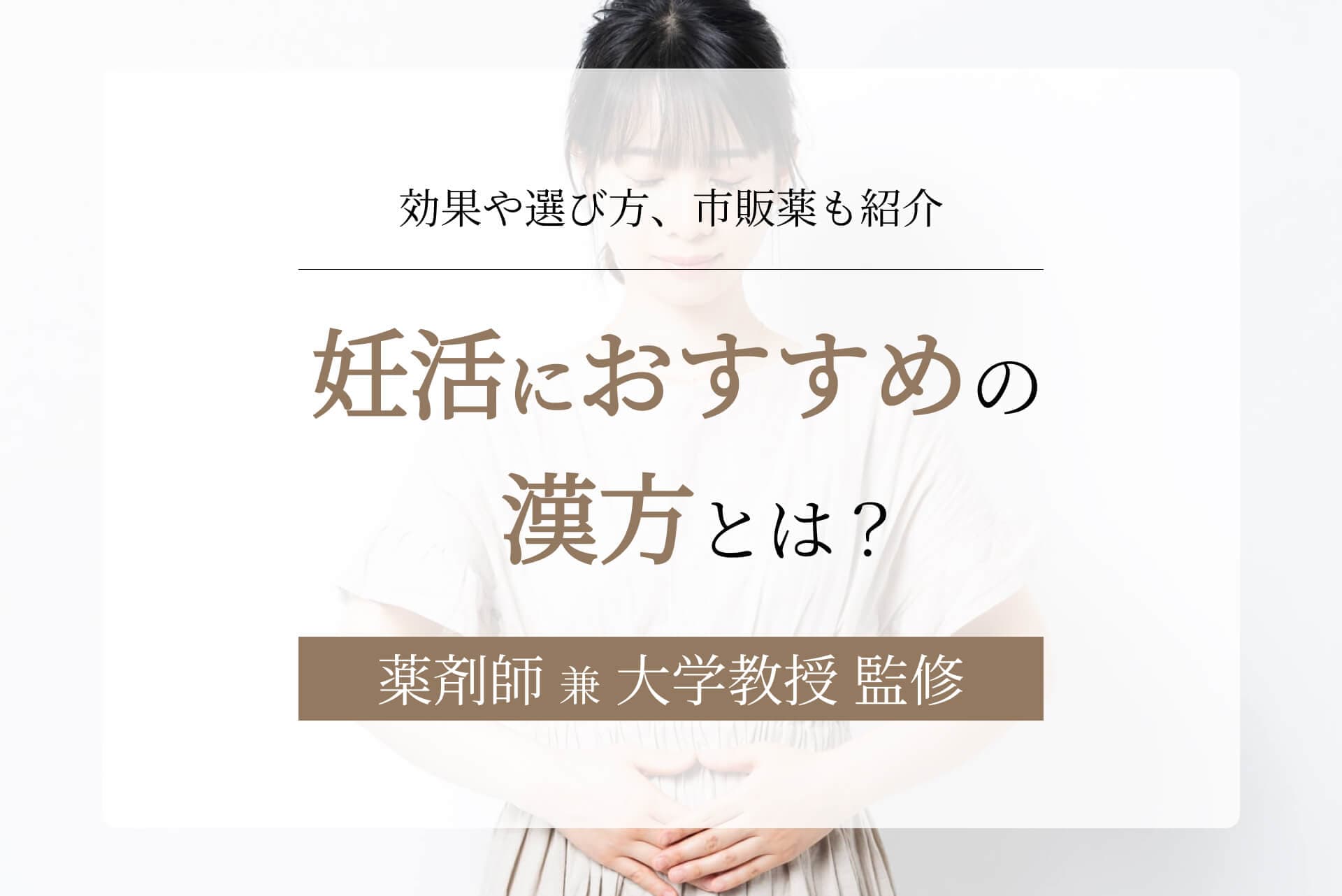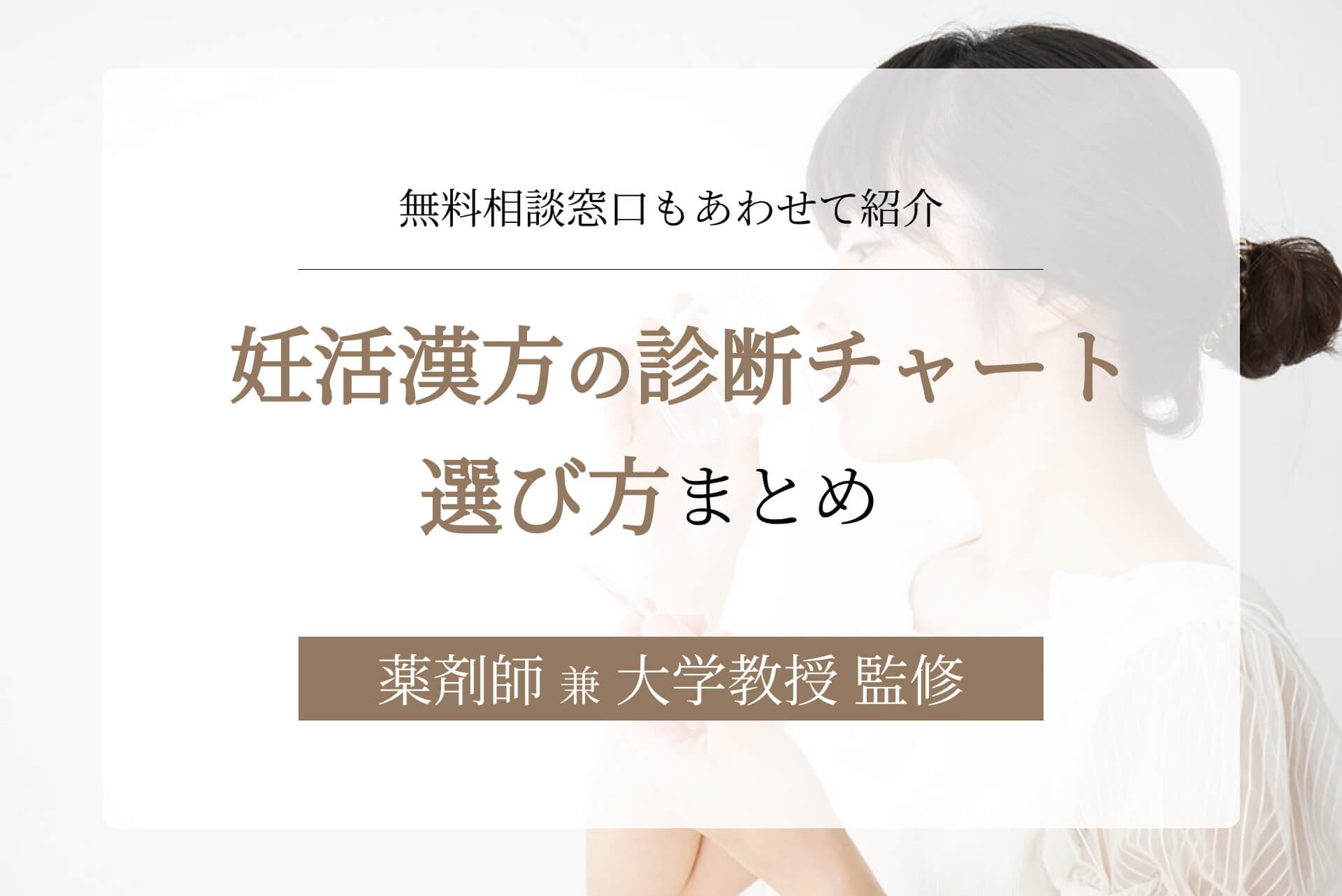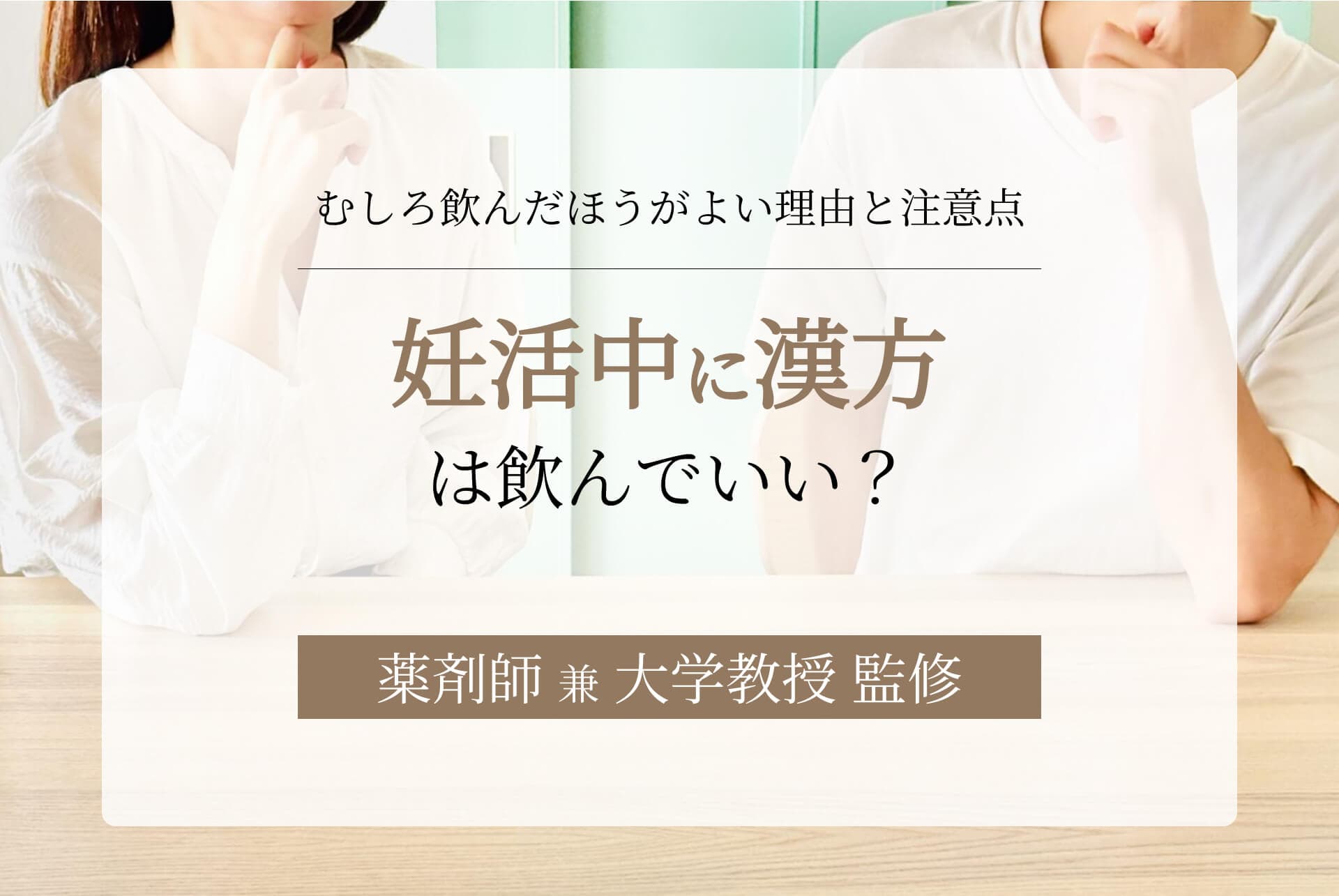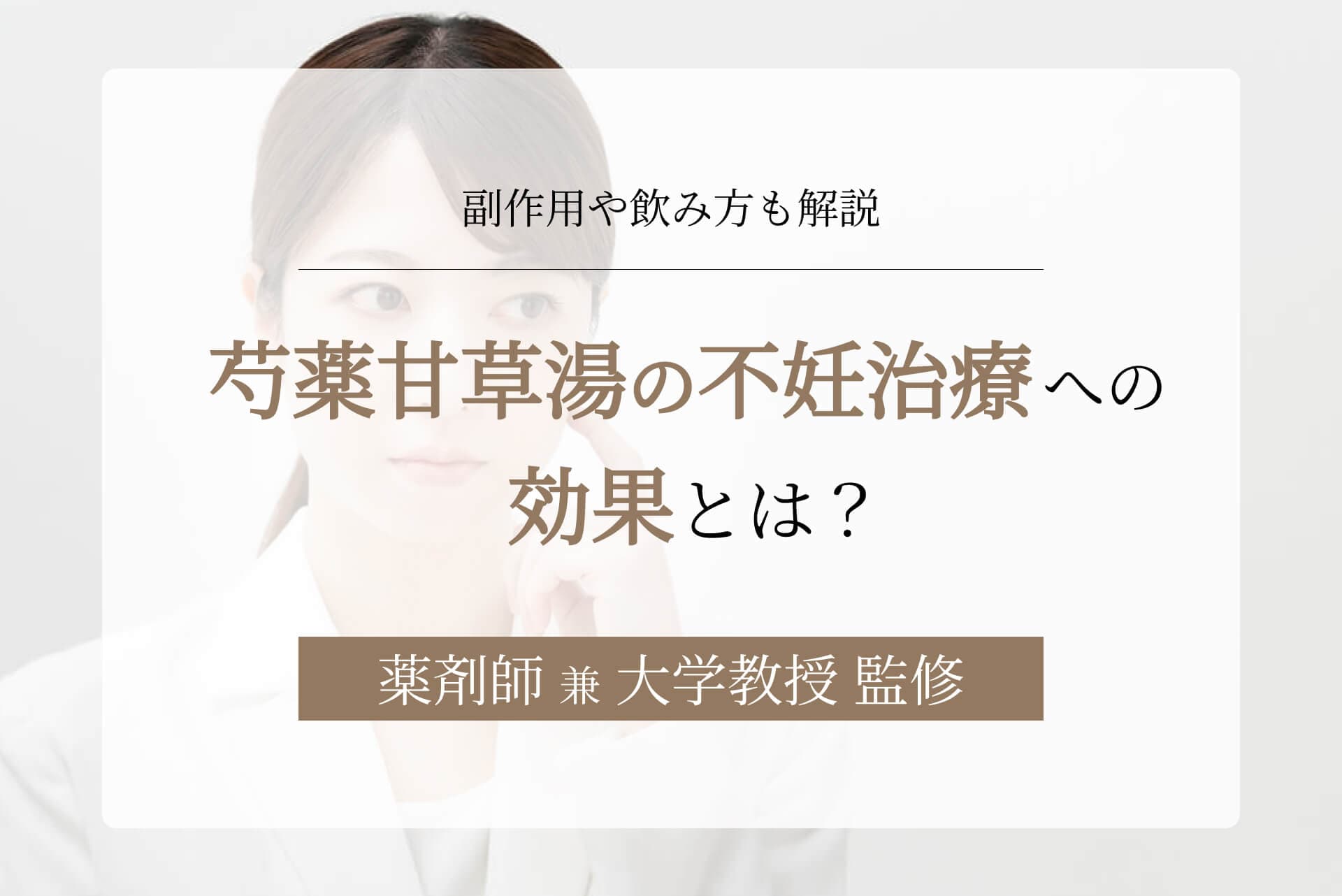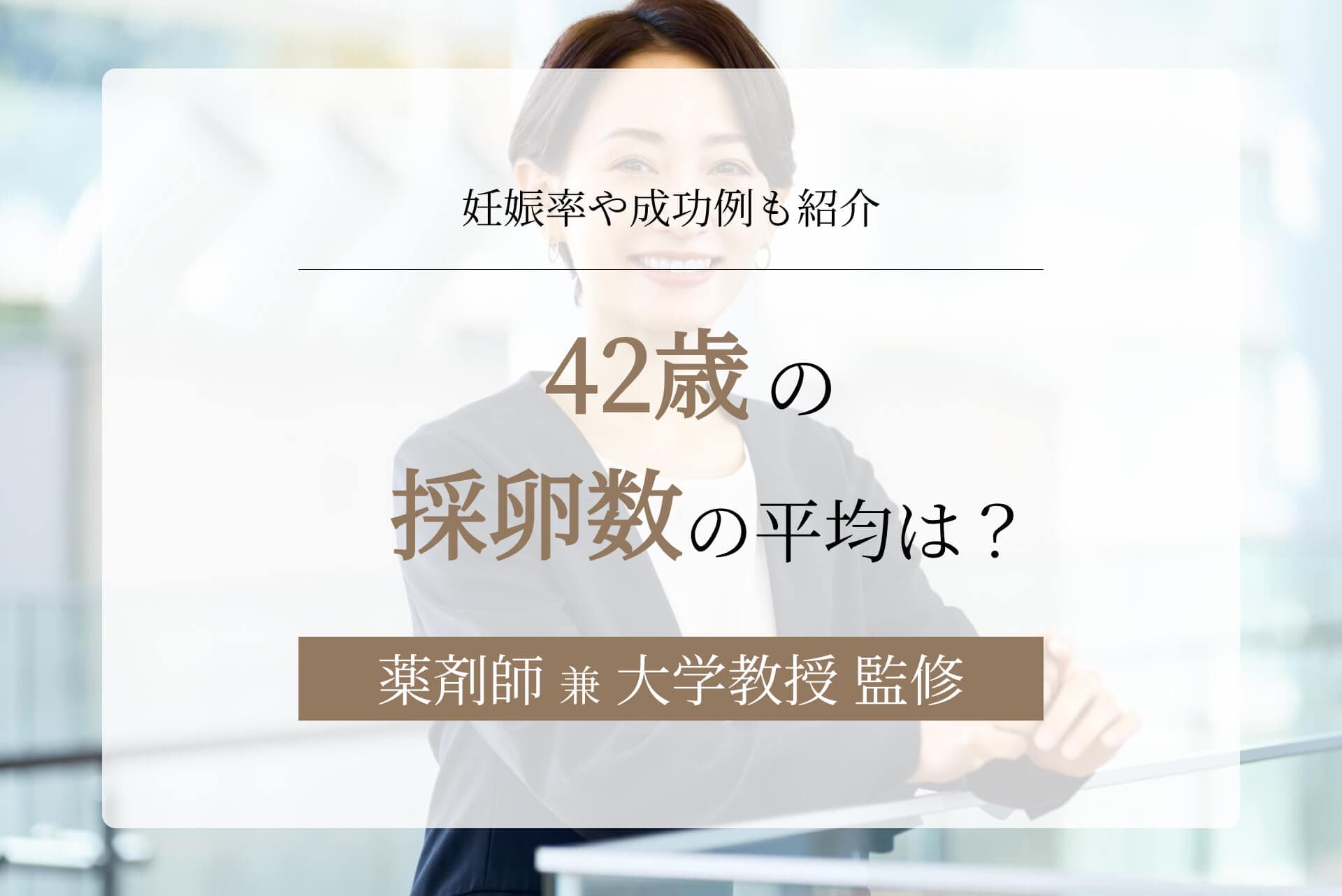妊活の漢方は保険適用?条件や自己負担額についても解説
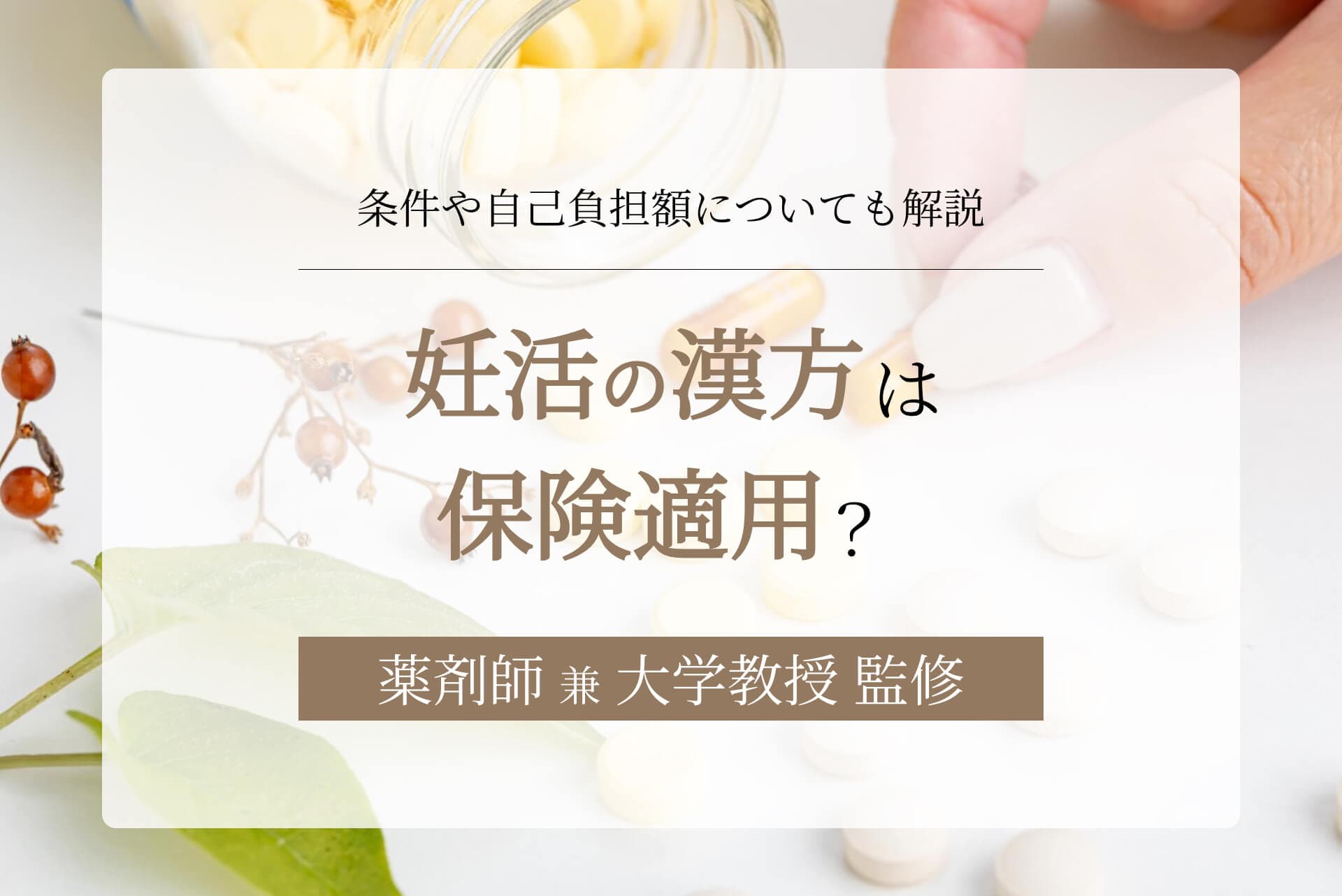
この記事を監修した人
妊活や不妊治療において、漢方薬がよく用いられます。しかし、漢方薬が保険適用になるのか、自己負担額がどのくらいになるのか気になりますよね。
そこで今回は、妊活・不妊治療の漢方の保険適用について解説します。男性不妊治療も含めた保険適用条件と自己負担額の目安や、保険適用される漢方薬の種類、医療機関の選び方についても解説していますので、ぜひ参考にしてくださいね。
漢方による妊活・不妊治療の費用の目安
妊活や不妊治療では、ホルモンバランスを整えたり、身体を温めたりして妊娠しやすい体質にすることが重要です。体質を改善して妊娠しやすい身体にするために使われる薬として、漢方薬が挙げられます。漢方薬は自律神経の乱れや冷えの改善、ストレスを軽減し、不妊治療で効果を発揮します。
通常、医師が処方する漢方薬は保険適用になります。保険適用の場合、自己負担は1〜3割です。漢方薬は長期で継続して飲むことが多いため、保険適用であれば高額にならず、安心ですね。
一方、薬局やドラッグストアで市販の漢方薬を購入した場合は、保険適用にはなりません。市販の漢方薬を1カ月間服用する場合は、漢方薬の種類にもよりますが、5,000円前後になることが多いでしょう。
また、妊活で服用する漢方薬はセルフメディケーション税制の対象にならないことが多いため、注意が必要です。
出典:
女性不妊|ツムラ
漢方の疑問点「Q&A」|日本東洋医学会
ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス顆粒A|ツムラ
セルフメディケーション税制と対象品について|ツムラ
漢方による妊活・不妊治療の保険適用条件
妊活や不妊治療で漢方薬を服用したい方は、保険適用になるのか気になりますよね。本章では、妊活や不妊治療における漢方薬の保険適用の条件について解説します。ぜひ参考にしてくださいね。
保険医療機関の医師に処方してもらうこと
保険適用になる薬を処方してもらうためには、保険医療機関に指定されている病院や診療所を受診する必要があります。マイナ保険証等を提出することで、保険診療を受けられますよ。
医師が患者を診察して診断したうえで、必要とされる薬が処方されます。処方された薬は保険適用となり、自己負担は1〜3割です。
出典:健康保険で受けられる診療と受けられない診療|SCSK健康保険組合
保険適用可能な薬であること
保険適用される薬は、厚生労働省が定める「薬価基準」に収載されている薬に限られます。医療機関等で保険診療に用いられる薬は医療用医薬品と呼ばれ、現在、薬価基準に収載されている医療用医薬品は約1万3千品目ほどあります。医療用医薬品には漢方薬も含まれ、その数は約580品目です。
保険医療機関の医師が薬価基準に収載されている医療用医薬品の中から症状に合う薬を選び処方することで、保険適用となります。もし薬価基準に収載されていない薬が処方された場合、薬代は全額自己負担となるため高額になるおそれがあります。
出典:医療用漢方製剤 2024 -148 処方の添付文書情報- |日本漢方生薬製剤協会 医療用漢方製剤委員会 有用性研究部会
不妊治療に関係する薬であること
処方される薬が保険適用となるには、症状の治療・緩和を目的とする薬である必要があります。
そのため、不妊治療で受診している場合、不妊治療に関係ない薬は保険適用にはなりません。直接不妊症を改善する薬でなくても、体質改善やストレスの緩和に用いられる薬であれば保険適用になるでしょう。
出典:健康保険で受けられる診療と受けられない診療|SCSK健康保険組合
漢方による男性の妊活・不妊治療も保険適用になる?
男性の妊活・不妊治療に用いられる漢方薬も、保険適用になります。
不妊に悩むカップルの半分は男性不妊が原因です。男性不妊の原因として、精子の量が少ないことや、精子の質が低いなどの問題が挙げられます。漢方薬を服用することで精子の質が改善する可能性があるため、男性の妊活・不妊治療にも漢方薬が用いられることは多いでしょう。
男性の妊活・不妊治療の場合も、保険医療機関を受診し適切な漢方薬を処方してもらうことで、保険適用になります。男性の不妊治療には、生殖機能である「腎」の機能が低下している「腎虚」を改善する漢方薬が用いられます。
腎を補う「補腎剤」として、「八味地黄丸」という漢方薬が多く使われています。また、同様に補腎剤である「牛車腎気丸」や「補中益気湯」も男性の不妊治療に用いられることの多い漢方薬です。
出典:男性不妊症と漢方|東京医科大学病院 漢方医学センター
保険適用される漢方の種類と効果
現在承認されている漢方薬は294処方あり、そのうち148処方が医療保険の適用となります。保険適用の範囲内の漢方薬では、効果が低いのではないかと心配な方も多いでしょう。
そこで、本章では保険適用される漢方薬の種類や効果について解説します。妊活や不妊治療にどんな漢方薬が使われているのか、確認しておきましょう。
出典:漢方薬の基礎知識|神奈川県
温経湯
東洋医学では、私たちの体は「気・血・水」のバランスによって健康が維持されていると考えられています。不妊の原因の1つとして、体全体に栄養や熱を運ぶ「血(血液)」が少ないことが挙げられます。
温経湯は「血」が不足した状態(血虚)を改善する効果のある漢方薬です。血を補うことで血行がよくなり、卵巣や卵子に栄養が十分行き渡るようになります。また、血液の流れがよくなると体が温まり、不妊の大敵である冷えを改善します。
出典:温経湯|ツムラ
桂枝茯苓丸
桂枝茯苓丸は滞った「血」の巡りを改善する効果のある漢方薬です。「血」の流れが滞ると、上半身はのぼせやすく、下半身は冷えやすくなります。桂枝茯苓丸は血行不良を改善することで下半身に栄養を行き渡らせ、月経不順や月経異常、生理痛などの症状を改善します。
また、卵巣や卵子に栄養が届くと、卵子の質が高まると考えられています。加齢や生活習慣によって低下する可能性のある卵子の質は、漢方薬の服用によって改善できるでしょう。
出典:桂枝茯苓丸|Kracie
加味逍遙散
加味逍遙散は不足した「血」を補い、「気(エネルギー)」の巡りをよくする効果のある漢方薬です。「血」の不足は生殖機能の低下につながり、「気」の巡りが悪いとイライラや不眠を引き起こします。加味逍遙散は「血」と「気」のバランスを整えることで、生理周期に伴うイライラや不眠、精神不安定などの神経症状を改善します。
出典:加味逍遙散|Kracie
漢方を使用した妊活・不妊治療費の自己負担額の目安
漢方薬を使用した妊活や不妊治療での自己負担額は、使用する漢方薬や服用方法、患者の負担割合などによって異なります。また、同じ漢方薬でも、販売しているメーカーや剤型(錠剤・散剤)などによっても値段が異なる場合があります。
今回は、妊活や不妊治療でよく使用される漢方薬を1日3回、30日間服用した場合の金額の目安を算出しています。以下に示すのは薬代だけで、診察料や指導料などは加味していないので注意してくださいね。
漢方薬 | 1日あたり(7.5g)の薬代 | 30日あたりの薬代 | 3割負担の場合の金額 |
|---|---|---|---|
ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) | 111.6円 | 3,348円 | 1,010円 |
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒(医療用) | 105.75円 | 3,172.5円 | 960円 |
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒(医療用) | 119.25円 | 3,577.5円 | 1,080円 |
上記の漢方薬の場合、それぞれ1カ月あたり1,000円前後で服用できることがわかります。市販の漢方薬を服用するよりも安価で継続しやすいでしょう。
保険適用外の漢方を使用した妊活・不妊治療について
保険適用外の漢方薬には自費診療による漢方薬と、OTC医薬品の漢方薬の2種類があります。本章では、それぞれどのような特徴があり、どのくらいの金額がかかるのか解説します。
自費診療による漢方薬
薬価基準に収載され、保険適用される漢方薬は約150種類あります。しかし、よりその人の証(体質、体力、抵抗力、症状の現れ方などの個人差)に合った漢方薬が必要な場合には、自費診療機関によって漢方薬を処方してもらう方法があります。
自費診療の漢方薬では、煎じ薬で治療を行います。生薬の種類や配合の量を自由に調合できるため、一人ひとりに合ったきめ細かな処方が可能です。保険適用内の漢方薬では症状が改善しない方や、より効果の高い漢方薬をお求めの方に適しているでしょう。
自費診療の漢方薬では、高品質の生薬を使用することがあります。また、使用する生薬の品目数に限りがありません。そのため、保険適用の漢方薬よりも高額になりやすいという特徴があります。
妊活・不妊治療の漢方薬の場合、体質や症状の度合いなどによっても異なりますが、1カ月あたり20,000円~40,000円程度かかることが多いです。また、漢方薬は長期服用によって効果を実感できることが多いため、3カ月程度継続する必要があるでしょう。
出典:保険適用外の漢方 自費診療機関頼み|北里大学
OTC医薬品の漢方薬
漢方薬の一部は、薬局やドラッグストアでも販売されています。薬局やドラッグストアで購入できる漢方薬はOTC医薬品の「第2類医薬品」に分類され、294種類が規定されています。
病院で処方される医療用医薬品の漢方薬の用量を調節して作られているのが、OTC医薬品の漢方薬です。病院を受診しなくても、気軽に購入して試せるのがメリットです。どの漢方薬がよいか迷ったときには、薬剤師や登録販売者に相談してくださいね。
妊活・不妊治療に使用される漢方薬である温経湯、桂枝茯苓丸、加味逍遙散などは、OTC医薬品としても販売されています。下記の表は、OTC医薬品の漢方薬の金額の例です。
商品名 | 包装・希望小売価格 | 成分量 |
|---|---|---|
ルナフェミン(温経湯) | 168錠(14日分)3,850円 | 医療用医薬品の半分 |
ツムラ漢方桂枝茯苓丸料エキス顆粒A | 20包(10日分)2,640円48包(24日分)4,730円 | 医療用医薬品の半分 |
ツムラ漢方加味逍遙散エキス顆粒 | 20包(10日分)2,640円48包(24日分)4,730円 | 医療用医薬品の半分 |
保険適用になる医療用医薬品では、3割負担の場合、1カ月1,000円前後で服用できます。このことから、OTC医薬品での服用は保険適用の漢方薬に比べて割高になることがわかります。また、成分量は医療用医薬品の半分になり、効果が十分に感じられない可能性があるため注意が必要です。
出典:漢方薬の飲み方と効能を知る|ツムラ
漢方治療と西洋医学を併用する場合の妊活・不妊治療の保険適用について
医療機関を受診して妊活や不妊治療を行う場合、漢方薬での治療と西洋医学での治療を併用することが多いでしょう。この場合の注意点や、保険適用の範囲について解説します。
併用時の注意点
漢方薬に限らず、複数の薬を服用すると薬同士が作用し合い、体に悪影響を及ぼすことがあります。薬の飲み合わせが悪いと、片方の薬の効果が強くなり副作用が出てしまったり、逆に効果が弱まって症状が改善しなかったりするため注意が必要です。
漢方薬と西洋薬で併用してはいけない組み合わせの例は、「小柴胡湯」と「インターフェロン製剤」です。間質性肺炎が現れるおそれがあるため、一緒に服用できません。
また、生薬のうち「麻黄」が含まれる製剤は、一部の喘息薬や抗うつ薬との組み合わせが併用注意となっています。さらに、「甘草」が含まれる製剤は降圧剤や利尿剤と併用すると、むくみや手足のしびれなどの副作用が発現する可能性があるため、注意しましょう。
また、漢方薬で注意しなければいけないことは、生薬の重複です。漢方薬には複数の生薬が含まれています。複数の漢方薬を服用する場合、同じ生薬が配合されていないか確認しましょう。
薬を併用する場合は、かかりつけの医師や薬剤師、登録販売者に確認してくださいね。
出典:ツムラ漢方製剤エキス顆粒(医療用)漢方薬の相互作用について|ツムラ
保険適用の範囲
不妊治療は、治療内容によって保険適用の範囲が定められています。タイミング法や人工授精といった一般不妊治療には、年齢や回数の制限はありません。一方、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療(ART)には、年齢や回数の上限が設けられています。
保険適用となる生殖補助医療の条件は、治療開始時点で女性の年齢が43歳未満であることです。また、保険が適用される回数の上限は「胚移植の回数」を基準とし、以下のように定められています。
初めての治療開始時点の女性の年齢 | 回数上限 |
|---|---|
40歳未満 | 通算6回まで(1子ごと) |
40歳以上43歳未満 | 通算3回まで(1子ごと) |
なお、治療の過程で処方される医薬品については、薬事承認された効能・効果、用法・用量の範囲内で使用される場合に保険適用となります。そのため、漢方薬に関しては年齢や回数の制限なく保険が適用される点も、不妊治療におけるメリットの一つです。
出典:
不妊治療に関する取組|こども家庭庁
不妊治療で使用される医薬品の保険給付上の取扱いについて|厚生労働省
保険適用で漢方での妊活・不妊治療を行う医療機関の選び方
保険適用での妊活・不妊治療を希望する方は、どのように病院を選べばよいか気になりますよね。
病院によっては漢方薬をあまり使用しなかったり、自費になったりする場合があります。正しい病院の選び方を確認しておきましょう。
病院を選ぶ際は、以下のことに気を付けましょう。
- 自費診療ではなく保険診療を行っているか
- 通院しやすい場所・診療時間か
- 望んでいる不妊治療を行えるか
保険適用で漢方薬を処方してもらうためには、保険医療機関を受診する必要があります。また、一般的に不妊治療では1カ月に複数回の受診が必要です。
診療時間に間に合わなかったり、アクセスが悪くて通院時間が負担になったりしないよう、できるだけ通いやすい病院を選びましょう。
また、体外受精や顕微授精などの生殖補助医療を行っておらず、タイミング法や人工授精などの一般不妊治療しか実施していない病院も多くあります。途中で転院しなくてもよいように、今後どのような治療をしていきたいか考えてから病院を選択するとよいでしょう。
出典:第2回 治療への初めの一歩〜医療機関探しについて~|東京都福祉局
「漢方薬房こうのとり」が妊活のお悩みを解決するお手伝いをします◎
妊活や不妊治療において、漢方薬による体質改善は有効な選択肢のひとつです。体のバランスを整えたり、ストレスを緩和したりすることで、妊娠しやすい体づくりをサポートします。
ただし、漢方薬はその人の体質や症状に合った処方でなければ、十分な効果を得られない場合もあります。いくら保険が適用され経済的に続けやすくても、合わない漢方では意味がありません。
服用を検討される際は、医師や専門の漢方薬局で丁寧なカウンセリングを受け、ご自身に合った漢方薬を選ぶことが大切です。
北陸・富山の「漢方薬房こうのとり」では、妊活や不妊治療に精通した専門スタッフが、丁寧にお話を伺いながらオーダーメイドで処方を行っています。
現在は、以前(2014年~2023年途中)使用していた「桃福宝」に比べ、より早く結果が出やすく、かつ2割以上価格を抑えた新処方の漢方薬を提供しています。費用面でも安心してご相談いただけます。
また、「漢方薬房こうのとり」では保険適用の漢方薬と同一処方のものは、特に品質に優れた2種の例外を除き使用しておらず、独自の処方で効果を追求しています。
妊活に関する疑問や、保険・助成金の活用についてもご相談いただけます。店舗でのカウンセリングはもちろん、オンライン相談も可能です。気になることがあれば、ぜひお気軽にご相談ください。