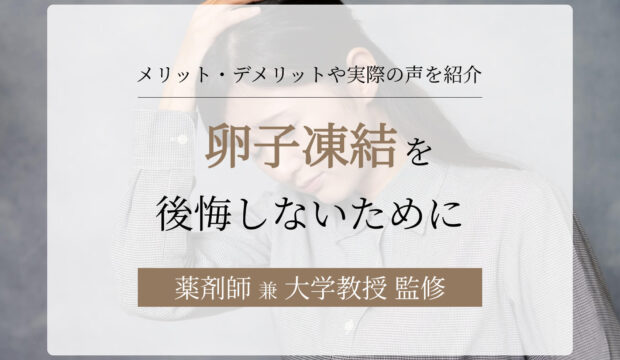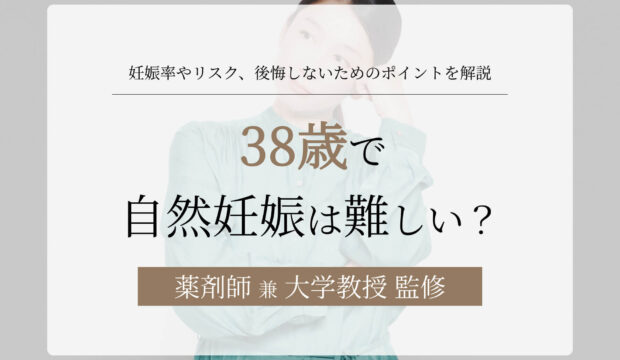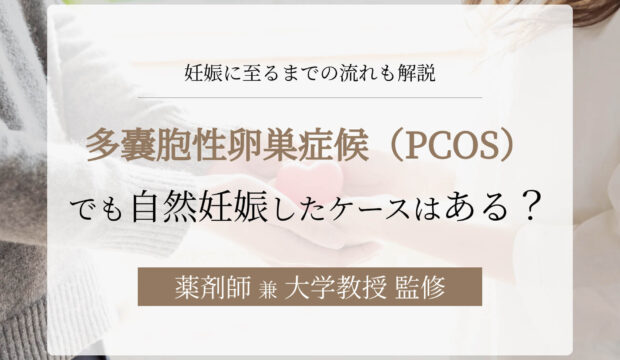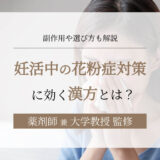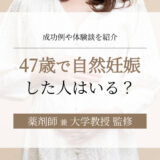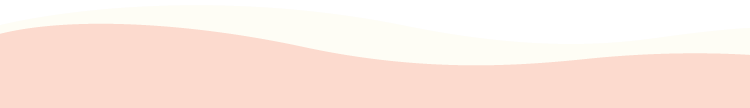現代の女性はストレスや生活習慣の乱れなどから、気づかないうちに“隠れ冷え性”の状態になっていることがあります。
実際、冷えを改善したことで体調が整い、妊娠につながったという声も少なくありません。
この記事では、妊活中の冷え対策として「温活」に着目し、基礎体温のリズムや妊活の時期ごとの温め方を含めて、日常生活に取り入れやすい実践方法をわかりやすくご紹介します。
今日からできることから始めて、妊娠しやすい体づくりを整えていきましょう。
妊活と体を温めること(温活)の関係
妊活において「体を温めること」は、とても大切なケアのひとつです。
体が冷えていると血流が悪くなり、子宮や卵巣へ十分な栄養や酸素が届かなくなるため、卵子の質や子宮内膜の状態、ホルモンバランスに悪影響を及ぼす可能性があります。
実際、「冷え性の改善によって妊娠に至った」という声は少なくなく、冷え対策=温活が妊活に有効であることは、多くの事例からも裏づけられています。
とくに女性の体はホルモンの影響を受けやすく、ストレスや生活習慣の乱れから「自覚のない冷え」を抱えている人も多いものです。
こうした“隠れ冷え性”を放置していると、生理不順、排卵の乱れ、着床障害といった不調が起こりやすくなります。
漢方の世界でも「冷えは不妊の大敵」とされており、体を温めて血流を整えることは、妊娠しやすい体質に近づくための基本とされています。詳しくは、以下の記事でも監修のもと解説しています。
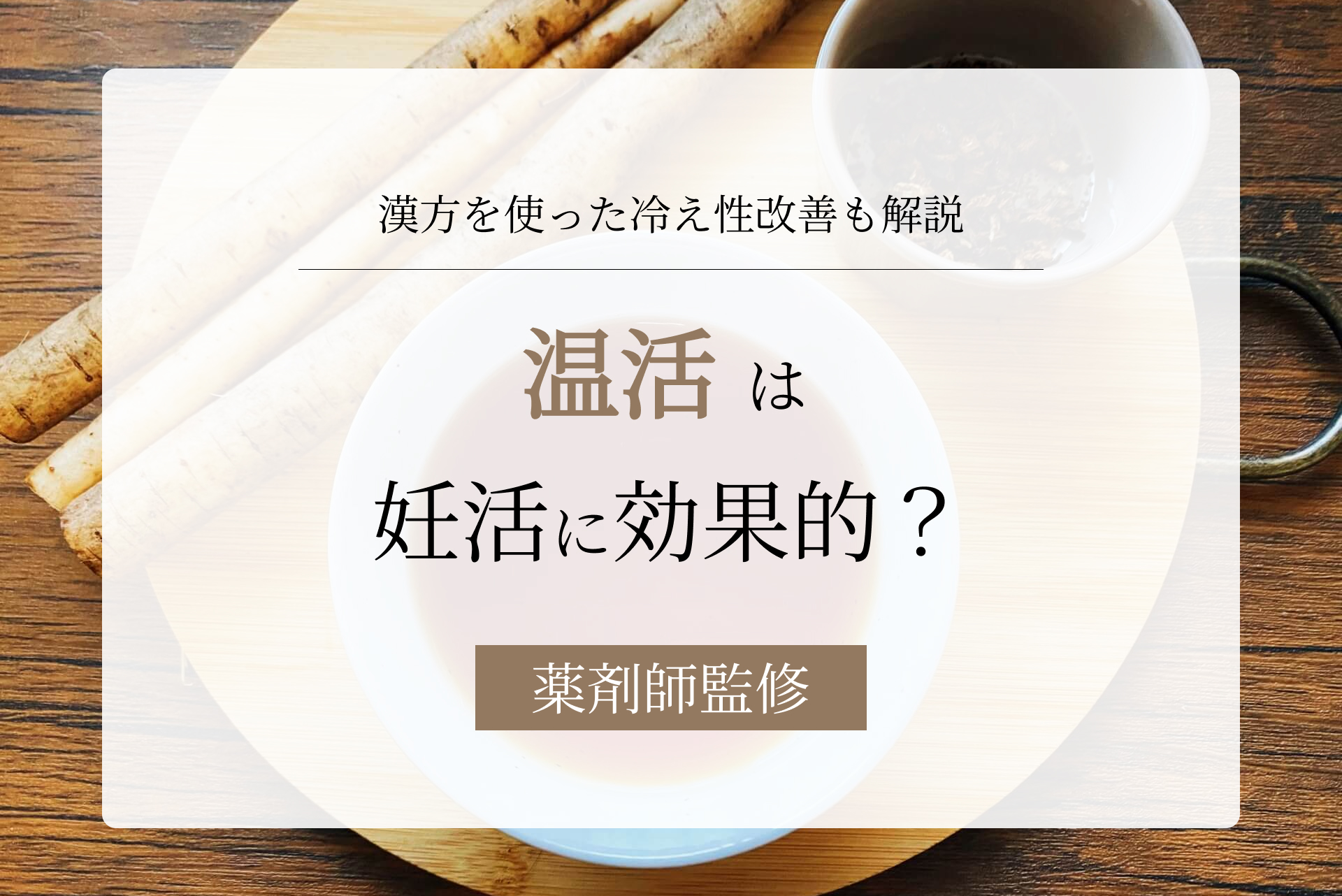
2023.10.05
温活は妊活に効果的?漢方を使った冷え性改善についても紹介
温活を妊活に取り入れることは効果的なのでしょうか?この記事では、妊活における「温活」について、また「冷え」が不妊に及ぼす影響について解説しています。さらに冷え性改善に効果的で、温活と相性の良い漢方についてもまとめています。実際に温活により妊娠した人の声も紹介しているので、妊活に役立ててくださいね。...
妊活で体を温めるべき時期は「基本的には通年」
冷えは一時的な不調ではなく、妊娠を目指す際の慢性的な問題です。
そのため、「冬だけ温める」では不十分で、体を温める=温活は1年を通じて意識したいケアといえます。
ではなぜ、妊活中は通年での温活が推奨されるのでしょうか。以下で理由を詳しく見ていきましょう。

『冷え外来』の著者であり、冷え性研究の第一人者として知られる川嶋朗医師によると、「冬に冷えを感じる女性(冬冷え者)」は全体の50.1%、「夏に冷えを感じる女性(夏冷え者)」は40.8%にのぼることがわかっています。さらに、一年を通して冷えを訴える女性は31.2%に達し、約3人に1人が慢性的な冷えに悩んでいるという実態も明らかにされています。
通年温めるべき理由
まず前提として、妊娠の成立には以下のようなさまざまな要素が関わります。
- ホルモンバランスの安定
- 子宮内膜の厚み
- 排卵の質
- 着床環境 など
これらの要素は「血流」と「自律神経の安定」と深く関係しており、体の冷えはそれらを乱す引き金となります。
特に現代は、冷房や寒暖差の大きい環境、薄着のファッション、ストレスなどが重なり、季節を問わず“内臓が冷える”リスクが高い状況です。外は暑くても体の深部が冷えている女性は決して少なくありません。
漢方の視点では、冷えが続くと「腎(=生命力や生殖力の源)」や「脾(=栄養を巡らせる働き)」、「肝(=血の流れやホルモンの調整に関わる)」のバランスが乱れやすくなると考えられています。これにより、体全体のエネルギーが不足し、妊娠に必要な働きが滞りやすくなるとされるのです。
夏場こそ「冷え」に要注意
「温活は冬だけ」と思われがちですが、実は夏こそ要注意の季節です。
冷房の効いたオフィスや電車、アイスや冷たい飲み物の摂りすぎなど、自覚のないうちに体が冷えているケースが多く見られます。実際、夏に手足の冷えやお腹の張り、生理不順を訴える女性は少なくありません。
冷えはじわじわと血流を悪化させ、体の働きを鈍らせます。その影響はすぐに表れるとは限りませんが、気づかぬうちに「妊娠しにくい体質」へ近づいてしまうこともあるのです。
体を「冷やさない」生活習慣を年中意識することが妊活の基本
体を温めるというと、「温かい飲み物を飲む」「腹巻きを使う」といった一時的な対策を思い浮かべがちですが、妊活ではもっと広い視点が必要です。
- 薄着や締めつけの強い服を避ける
- 朝食を抜かず、代謝を落とさない
- 湯船にしっかり浸かる
- 寝不足やストレスをためない
これらはすべて、体の深部を冷やさず、血の巡りを保つために大切な生活習慣です。
「温活=冬の一時的なケア」ではなく、通年を通じた冷やさない生活を土台からつくっていくことが、妊娠しやすい体づくりにつながるという意識を持ちましょう。
妊活中の各時期と体を温めるときのポイント
妊活中は、ホルモンバランスや体調の変化に応じて体の冷え方も異なります。
ここでは、妊娠に向けたサイクルの中で特に重要な排卵期・着床期・生理期の3つの時期に分けて、温め方のポイントを解説します。
排卵期(排卵前後)
排卵を控えたこの時期は、卵胞の成長やホルモンの変化によって自律神経が不安定になりやすく、お腹や足先の冷えを感じやすい時期です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 冷えの状態 | 下腹部や足先が冷えやすく、血流の滞りを感じやすい |
| 温め方のポイント | 下腹部と足元を中心に、やさしくじんわり温める |
| 温める場所 | おへその下(丹田)、足首、内くるぶし付近、ふくらはぎなど |
とくにこの時期は、過剰に温めすぎるよりも“巡りをよくする”意識が大切です。湯船につかる・軽いウォーキングなどで、内臓の冷えを防ぎましょう。
着床期(排卵後〜生理予定日まで)
受精卵が着床しやすい環境を整えるために、子宮内膜を育てる“温かさ”が必要な時期です。
冷えによる血行不良は着床の妨げになる可能性があるため、特に注意しましょう。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 冷えの状態 | お腹の深部が冷えやすく、下腹部の張りや違和感を感じることも |
| 温め方のポイント | 子宮まわりをじっくり温めて、血の巡りとホルモン分泌をサポート |
| 温める場所 | お腹(下腹部・腰)、仙骨まわり、骨盤まわり、太もも |
この時期は、腹巻きや湯たんぽなどで「お腹と腰の両面を温める」ことがポイントです。
また、足元の冷えにも注意して、足首を冷やさないようにしましょう。
生理期(生理中)
生理中は体温が下がりやすく、全身の巡りが鈍くなりがちです。
この時期の冷えは「瘀血(おけつ)」と呼ばれる血の滞りを助長し、次の排卵や受精に悪影響を与えることもあります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 冷えの状態 | 全身の冷え・お腹の重だるさ・下腹部の鈍痛などを感じやすい |
| 温め方のポイント | やさしく保温し、体を締めつけない服装や姿勢でリラックスを心がける |
| 温める場所 | 腰まわり(仙骨)、足首、足裏、ふくらはぎ |
生理痛がある場合や出血量が多い場合は、「温めすぎない」ことも大切です。蒸気温熱シートなど、じんわり優しく温まるグッズを使いましょう。
基礎体温の「低温期」と「高温期」で意識を変えるのもアリ
基礎体温の変化は、ホルモンバランスや体の状態を知る大切なサインです。基礎体温には「低温期」と「高温期」の2つの相があり、それぞれの時期で体の冷え方や温活のアプローチも変えると、より効率的に妊娠しやすい体づくりをサポートできます。
低温期(生理終了~排卵まで)
低温期は、卵胞が成長し排卵の準備が進む大切な時期。基礎体温が最も低くなるタイミングでもあり、体が冷えやすく、血の巡りも不安定になりやすいといわれています。
この時期の温活では、「内側から温めて巡らせること」がカギになります。
朝に白湯を飲んだり、冷たい飲食を控えるなど、小さな習慣から体を冷やさない意識を持ちましょう。
高温期(排卵後~生理開始まで)
高温期は、黄体ホルモン(プロゲステロン)の働きにより体温が自然と上がります。
子宮内膜を厚くし、受精卵が着床しやすい状態を整える時期です。
この時期に無理に温めすぎると、体の熱がこもって睡眠の質が下がったり、のぼせ・イライラにつながることもあるため、「温める」から「冷やさない」意識へシフトするのがおすすめです。
このように、基礎体温のリズムに合わせて温活の方法を少し調整するだけでも、妊娠に適した体内環境を整えることが期待できます。
成功事例から学ぶ、妊活における温活の時期
温活は妊活をサポートする方法のひとつとして注目されていますが、実際に妊娠に至った方々の声から学べることもたくさんあります。
ここでは、温活を生活に取り入れたことで妊娠につながった事例を2つご紹介します。
生理中の温活で「冷え体質」を脱し、妊娠へ
30代前半/会社員/タイミング法併用
生理中は出血のため体が冷えやすく、毎回お腹の痛みやだるさに悩んでいたAさん。妊活を始めてから、生理中でもカイロやレッグウォーマーを使って腰・足元を温めるようにしたそうです。
また、毎晩湯船に浸かる習慣をつけたところ、次第に基礎体温が安定し、月経痛も軽減。数ヶ月後には自然妊娠に至りました。
「生理中は無理に温めちゃいけないと思っていましたが、“じんわり保温”が合っていたみたいです」
夏場の冷房対策が体調の安定と妊娠に
40代前半/パート勤務/不妊治療経験あり
Bさんは夏でも手足が冷たく、基礎体温のグラフもギザギザで不安定でした。職場の冷房が強く、1日中体が冷えきっていたといいます。
そこで、夏でも腹巻き・足首の保温・温かい飲み物を意識的に取り入れた結果、体温が安定し排卵日も把握しやすくなったとのこと。
その後、クリニックでのタイミング指導を受けながら、妊娠に成功しました。
「“夏でも冷える”という気づきが、体づくりの分岐点でした」
妊活・温活をサポートするほかの選択肢とそれを行う時期
温活は、妊娠に適した体づくりの基盤となりますが、それだけで万全というわけではありません。体を温めながら、内側から整える“プラスα”のケアを取り入れることで、より妊活の可能性が広がります。
ここでは、温活と相性がよく、妊活の成功を後押しする3つの選択肢をご紹介します。
漢方の併用
冷え性の根本的な体質改善をめざすなら、漢方の併用は非常に有効な選択肢です。
漢方は、一人ひとり異なる体質や冷えのタイプに合わせてアプローチできるため、「温めてもなかなか改善しない」という人にも適しています。
とくに妊活中は、以下のような体の状態に着目し、必要な処方が選ばれます。
| 体質タイプ | 主な特徴 |
|---|---|
| 気虚タイプ | 冷えやすい/疲れやすい/胃腸が弱い |
| 血虚タイプ | 貧血ぎみ/月経量が少ない/肌が乾燥しやすい |
| 瘀血タイプ | 血の巡りが悪い/生理痛が重い/経血に塊があることが多い |
温活と漢方の併用は、冷えによるホルモンバランスの乱れや血流の滞りを根本から整えるサポートとして最適です。
とくに「基礎体温が安定しない」「生理周期がバラバラ」という方は、早めの相談をおすすめします。
適度な運動
運動不足も冷えを招く大きな要因のひとつです。
体を動かすことで血流が促進され、体温の維持やホルモンバランスの安定にもつながります。
激しい運動は必要ありませんが、ウォーキングやストレッチ、ヨガなどの軽い有酸素運動を週に2〜3回取り入れるだけでも、体がポカポカと温まりやすくなります。
特におすすめなのは以下のようなタイミングです。
| 時期 | 運動の目的と内容 |
|---|---|
| 低温期 | 排卵に向けた血流促進。ウォーキング・骨盤まわりのストレッチなど |
| 高温期 | 運動量を抑え、リラックス重視。深呼吸・軽いヨガなど |
| 生理期 | 基本は無理をせず、体調に応じてストレッチや軽い体操を |
栄養バランスの見直し
いくら外側から温めても、内側が栄養不足だと「温まる力」が育ちにくいのが妊活中の体です。
とくに以下の栄養素は、冷え改善につながりやすいでしょう。
| 栄養素 | 働きの例 |
|---|---|
| タンパク質 | ホルモン・免疫・筋肉の材料。基礎代謝を上げる |
| 鉄分・亜鉛 | 血液の材料。貧血予防や卵子の成熟に関与 |
| ビタミンB群 | 代謝サポートや自律神経の安定に必須 |
| ビタミンE | 血行を促進し、着床しやすい環境をサポート |
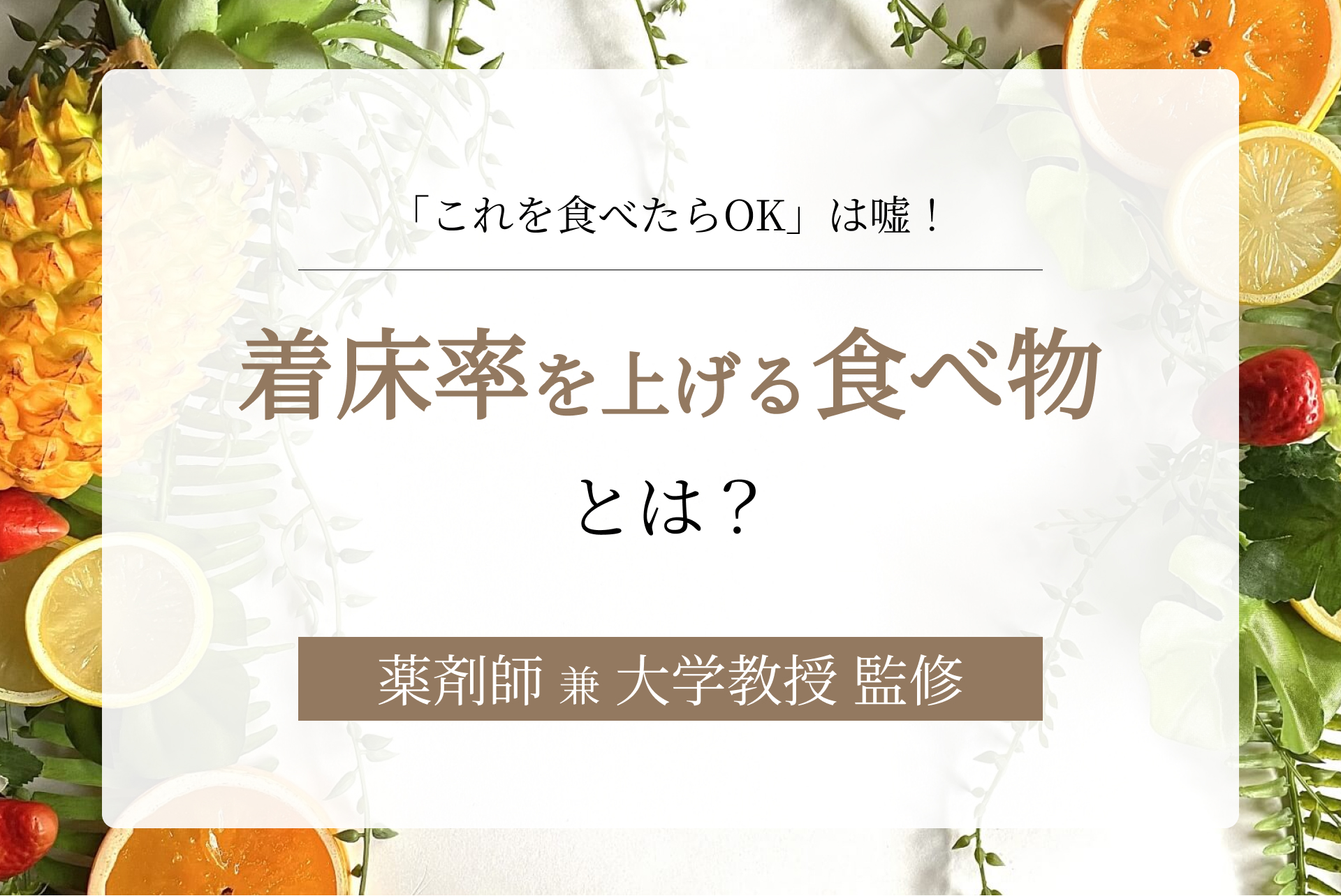
2023.11.06
着床率を上げる食べ物・飲み物はある?妊活にいい・わるい栄養(成分)とは
【薬剤師監修】食べ物や飲み物で着床率を上げたり子宮内膜を厚くしたりできたらよいですが、実は、食べ物からそれらに有効な成分を得るのは非常に難しいといえます。この記事では、その辺りについて現在わかっていることをまとめています。...
漢方薬房こうのとりでは生活習慣の見直しによる体質改善も徹底サポート◎
ここまでご紹介してきたとおり、妊活における冷えの影響は想像以上に大きく、日常のちょっとした温活が妊娠しやすい体づくりにつながります。
北陸富山の「漢方薬房こうのとり」では、これまで多くの妊活中の方々を、体質改善と生活習慣の見直しを通じて妊娠へ導いてきました。
実際の例を2つご紹介します。
1つ目は、卵子の質を低下させてしまうほどの「冷え」が原因で、基礎体温が生理前からすでに低温期になってしまうケースです。
2つ目は、生理の終わりかけ(5日目以降)に、薄い茶色のおりものが続くという冷え特有の症状です。
どちらも、冷えを解消すれば短期間で改善され、症状が出なくなることが多いのですが、本人が子宮や卵巣の冷えに気づいていないことが多く、見過ごされがちです。特に25歳以上の方は、日々の生活習慣に注意が必要です。
「漢方薬房こうのとり」では、こうした冷えの兆候を見逃さず、1人ひとりの体質や生活背景を丁寧にヒアリングしながら、最も適した方法を一緒に考え、ご提案しています。
専門知識を持つ薬剤師が、「冷えのタイプ」や「ホルモンの状態」、「日々の過ごし方」などを総合的に見極め、必要に応じて病院とも連携しながら、あなたに合った漢方や生活改善アドバイスを行います。
店舗でのご相談はもちろん、遠方の方にはオンライン相談にも対応しているので、妊活や不妊でお悩みの方は、ぜひお気軽に「漢方薬房こうのとり」へご相談ください。